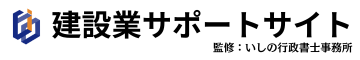目次
建設キャリアアップシステムとは
人手不足と高齢化が進む建設業では、若者の定着が喫緊の課題です。
拘束時間の長さと給与水準の低さが、若者の定着を拒む要因の一つとされています。就業率を上げるには、能力や実績が正しく評価される業界に変わることが必要です。
建設キャリアアップシステムを導入することで、就労管理や適切な施工経験の積み上げが可能になり、キャリア形成がしやすくなります。これにより、若者に対して「建設業は努力すれば稼げるようになる」とアピールできます。
建設キャリアアップシステムの狙い
- 適正な就労管理(長時間労働・サービス残業の是正、社会保険加入の徹底)
→ 健全さ、時間当たりの効率を重視する若者にアピール - 人材の育成の意識を企業に根付かせる
→ キャリア形成がしやすく将来計画を立てやすくなる - 能力や実績に基づく適正な評価による処遇の改善
→ 努力が評価に結びつく
建設キャリアアップシステムの重要性
建設キャリアアップシステムは今のところ義務化されていませんが、重要性が高まりつつあるようです。
国は建設キャリアアップシステムの導入を、経営事項審査の加点対象としました。このことから、さらに重要性が高まっていくことでしょう。
国交相は、すべての技能者が建設キャリアアップシステムに登録することを目指すと掲げています。今後もますます普及の流れが加速することが予測されます。
建設キャリアアップシステムにかかる費用
スクロールできます
| 登録料・更新料(税込) | |
|---|---|
| 事業者登録期限は5年 | 6,000円〜※1 |
| 技能者登録 | 簡略型 2,500円 詳細型 4,900円 |
| 管理者ID | 11,400円※2 |
※1 事業者登録料は資本金によって異なります。個人事業主は6,000円、一人親方は0円。
※2 毎年更新が必要です。一人親方は2,400円。
- 簡略型・・・とりあえず就業履歴の蓄積だけをすれば良い
- 詳細型・・・能力判定を受けてカードのレベルアップを目的とする
建設キャリアアップシステムの登録は行政書士へ
建設キャリアアップシステムの登録は、必要な資料の収集やデータの変換、そして独特な登録作業まで多大な手間を要します。
煩雑な作業に、大切な本業の時間を割くのはもったいないと考えています。
建設業の皆様には、ぜひ本業の工事に全力を注いでいただきたい。そのために、当事務所では登録代行を承っています。
貴社の事業がスムーズに進むよう、ぜひ私たち専門家にご相談ください。
初回は相談無料
\ お気軽にお問い合わせください /
記事が見つかりませんでした。